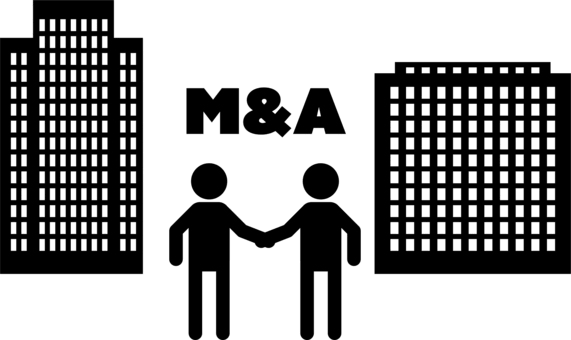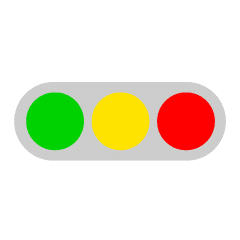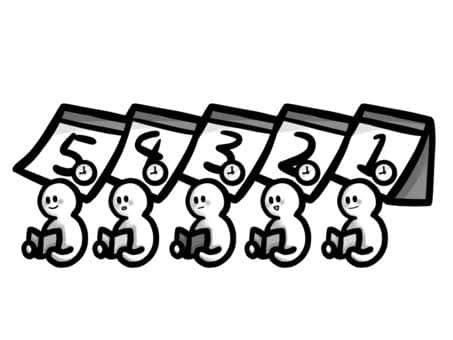どーもー!
お世話になっております!講師の杉渕です!
とんっでもない暑さで皆さま体調は崩されていないでしょうか。
私、体重100kgを超えているため、暑さにはかなり弱いのですが、炎天下の甲子園で全力でプレーする球児の皆さんを見ていると、自分ごときが「暑いって思うこと」が恥ずかしく思えてきます。なので、どれだけ暑くても「昨日よりは涼しいかも」「絶対ビールが美味しい気温だ」とポジティブに変換するように心掛けています。脳に無理矢理「暑くてもいいことがある」と思い込ませています。この作業に慣れてくると、暑くてしんどい時間が徐々に減ってくるのを実感できると思います。ぜひお試しいただきたいです。
このように、人は「○○と思い込むこと」を毎日繰り返していて、「○○だ」と思い込むことによって、物事が良い方向に進むこともあります。ただ、もちろん悪い方向にも進んでしまいます。会社組織においても、常に至る所で誰かが、誰か(何か)を「○○と思い込むこと」が日常的に繰り返されています。
最近、友人から聞いて驚いたのですが、部下が大きなミスをしてしまったときの口癖が「法的な措置をとるぞ」という経営者の方がいて、その部下の方は「ミスをしたら社長に訴えられる可能性がある」と思い込んでしまい、社長の指示が間違っていると分かっていても指示に従うようになってしまったとのことです。
皆さんに勘違いしていただきたくないのは、「部下にもっと暴言を吐いて“この社長には服従するしかない”と思い込ませろ!!!」という主旨ではございません。逆に「部下にもっと気を使って“良い社長”だと思い込ませろ!!!」でもございません。
経営者の皆さんにお伝えしたいのは、「部下は○○だと思い込んでいるのが前提」だということです。これは組織構造学の基礎の基礎でもある『個人の価値観、個人の感覚は全員違う』の理解と同じになります。
また個人の価値観や感覚は、個人の経験によって形成されるものです。会社で働く前に形成された価値観もあれば、会社で働いているうちに形成された価値観もあります。つまり、経営者が「俺と同じ感覚で部下が動いてくれる」と感じている場合、過去に経営者の皆さんと一緒に行動した経験を基にして、部下側も「そうするものだ」と思い込んでくれている可能性があります。
逆に「俺が思っていたことと全然違う行動を部下が取る」というエラーが起きている場合、部下に「その価値観を与えたのは経営者自身」「そう思い込ませてしまっているのは経営者自身」という可能性もあるということです。経営者が部下に対して過去に“A”と指示したことがあったので部下は“A”だと思い込んでいたり、経営者が違う社員に“B”と指示していたのを聞いたことがあり、その部下は“B”だと思い込んでいたりします。
そのため、必要になるのが『明確な指示』になります。経営者の皆さんは、部下は感覚や思い込みで行動してしまうことを理解し、『明確な指示』を出すことによってその感覚や思い込みを発動させないようにすることが大事になります。
「部下は○○だと思い込んでいるのが前提」「そう思い込ませていまっているのは自分自身が原因」という理解がない経営者は、自然と曖昧な指示が増えてしまいます。結果、「○○するのが当たり前だろ」「俺はそんなこと頼んでいない」と部下を他責で注意する機会も同時に増えてしまいます。自責の意識があれば「指示が曖昧だったかも。追加の指示を出そう」となり、“他責で注意して終わり”にはなりません。
ちなみに、冒頭でお話しした「法的な措置をとるぞ」が口癖の社長の元で働いている友人から先日、「他責の社長に従うしかない部下はどうすればいいの?」と聞かれました。他責の社長に対して「社長!それ他責ですよ!もっと自責で考えてください!そもそも指示が曖昧だったんですよ!」なんて、もちろん、絶対に言えません。部下側から、他責思考の社長を自責思考に変化させていくことは不可能だと思われます。
対処法としては、先ほどから経営者の皆さんにお伝えしている内容と同じです。「社長は○○だと思い込んでいる」「自分の感覚と社長の感覚は違う」を理解し、部下側から指示の不明確な部分を洗い出し、社長に確認することが必要になります。
他責思考の社長からは「そんなことも分からないのか!」と注意される可能性はあります。その注意をされた場合は、忍耐や我慢が必要になるかもしれませんが、「法的な措置をとるぞ」に比べれば精神的には穏やかだと思います。抜本的な解決案ではないため、友人には不満を言われましたが…。
経営者(上司側)は個人の価値観や感覚は全員違うこと、個人の思い込みがあることを理解し、明確な指示を出すことが重要になりますので、少しでも参考になったら嬉しく思います。また、部下側も個人の価値観や感覚が全員違うことを理解し、“上司とのズレ”を明確になるよう行動することにより、日々の不満やストレスを少しでも減らすことができれば嬉しく思います。
今回はかなりの長文になってしまいました。
最後まで読んでくださった方々、本当にありがとうございます!